うちの長男はいわゆる、発達障害。発達に大きく凸凹がある。ASD、ADHD、LD(学習障害)、DCD(発達性協調運動障害)、吃音。発達障害丸ごと全部、というのが長男の特性。
実は年中の次男も、発達相談中。彼も何らかの支援があった方が生きやすいだろうなと思って相談した。そう、彼もまた繊細な子。味覚、聴覚、嗅覚、触覚などに感覚過敏があり、変化にも敏感で、初めてのこと、大人数や人混みが苦手。何かあると固まってしまったり、吃音が出たり、癇癪となる。
長男と違うのは適応力。園児30人ほどの、目の届く小さな幼稚園ではなんとか上手くやれているようで、園ではほぼ問題ないという。担任の先生からも、大丈夫ですよと言われてる。そしておそらくこの「一見適応できる」ことで、療育先でも彼は発達障害の範囲外、グレーゾーンと判断されていそうだ。なんてったって、発達検査結果と診断を受ける面談が、本来予定されていた1月から3月に延期されたのだ。4月からの療育クラスが締め切られているはずの、3月に。急ぎじゃない案件という扱いの、その空気をひしひしと感じている(確定はしてないが)。しょぼん。
うん、なんとなくわかってた。他にもっと支援が必要なお子さんがいるのも、優先順位が低くなりそうなのも、長男ほど決定的ではないのも。わかってたけど、彼に凸凹があってそれなりに困ってて、今後小学校で困りそうなのは本当なんだよ。優しい、繊細な彼が生きやすいように、支援があればいいなと思ったんだよ。でも、発達障害というカテゴリーにいないと支援が受けられない。必要な支援を受けるのにカテゴリーが必要なのも、もやもやする。あーあ、またまたしょぼん。
そもそもグレーゾーンってなんだろう。人間みな、それなりに得意不得意があって凸凹はあるもの。成長速度も人それぞれ。それが多少のことは個性として認められ、支援される社会なら、グレーゾーンってないのでは?と思う。ただ、良くも悪くも同調圧力が強い日本、特に学校では、凸凹を個性として認め手助けするではなく、凸凹が「障害」カテゴリーとして支障があるから支援すると見なされるケースが多いと思うのだ。その余波に、グレーゾーンがあるのではなかろうか。定型と定型外、そしてその狭間。
グレーゾーン疑いの次男の話。彼は手助けがあれば、なんとかやっていけると思う。いまの幼稚園みたいに。でも、忙しい今の学校でそれは期待できない。手助けを、支援をお願いするなら、発達障害のカテゴリーに入るしかない。入らなそうだけど。入ったとて、支援が受けられるかは別だけど(これはまた別の話)。狭間のグレーゾーンには、ほぼ支援がない。まだわからないし、先のことを考えても仕方ないし、心配しすぎなことはわかっているつもりだけど。なんかもう八方塞がりな気がして最近沈みがち。大きくしょぼん。

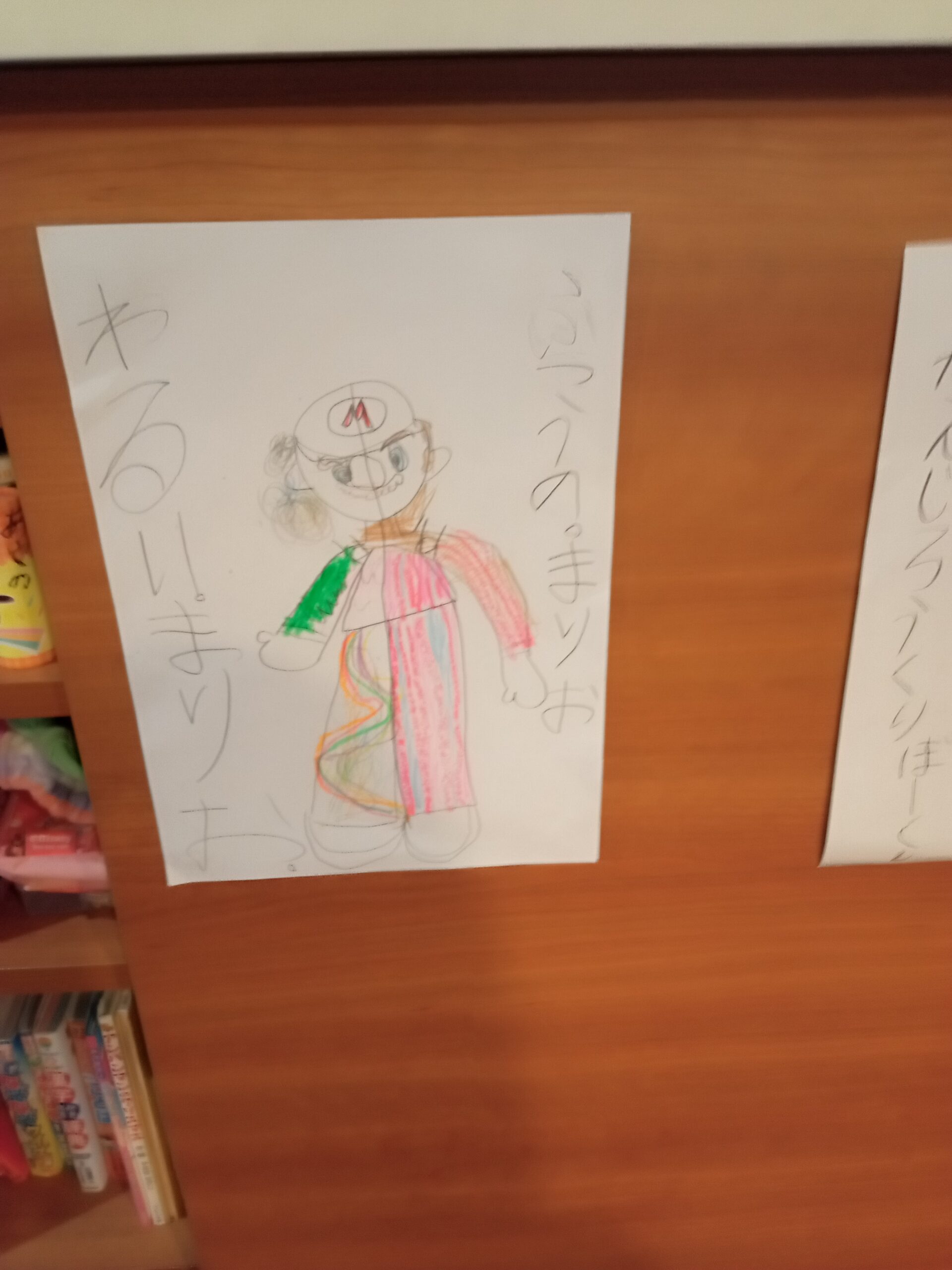

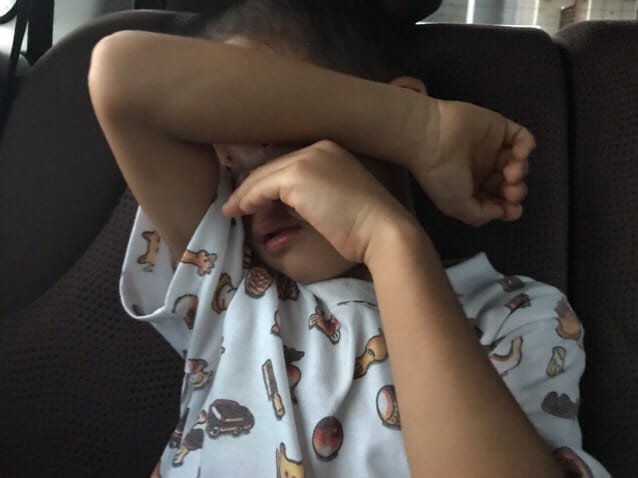


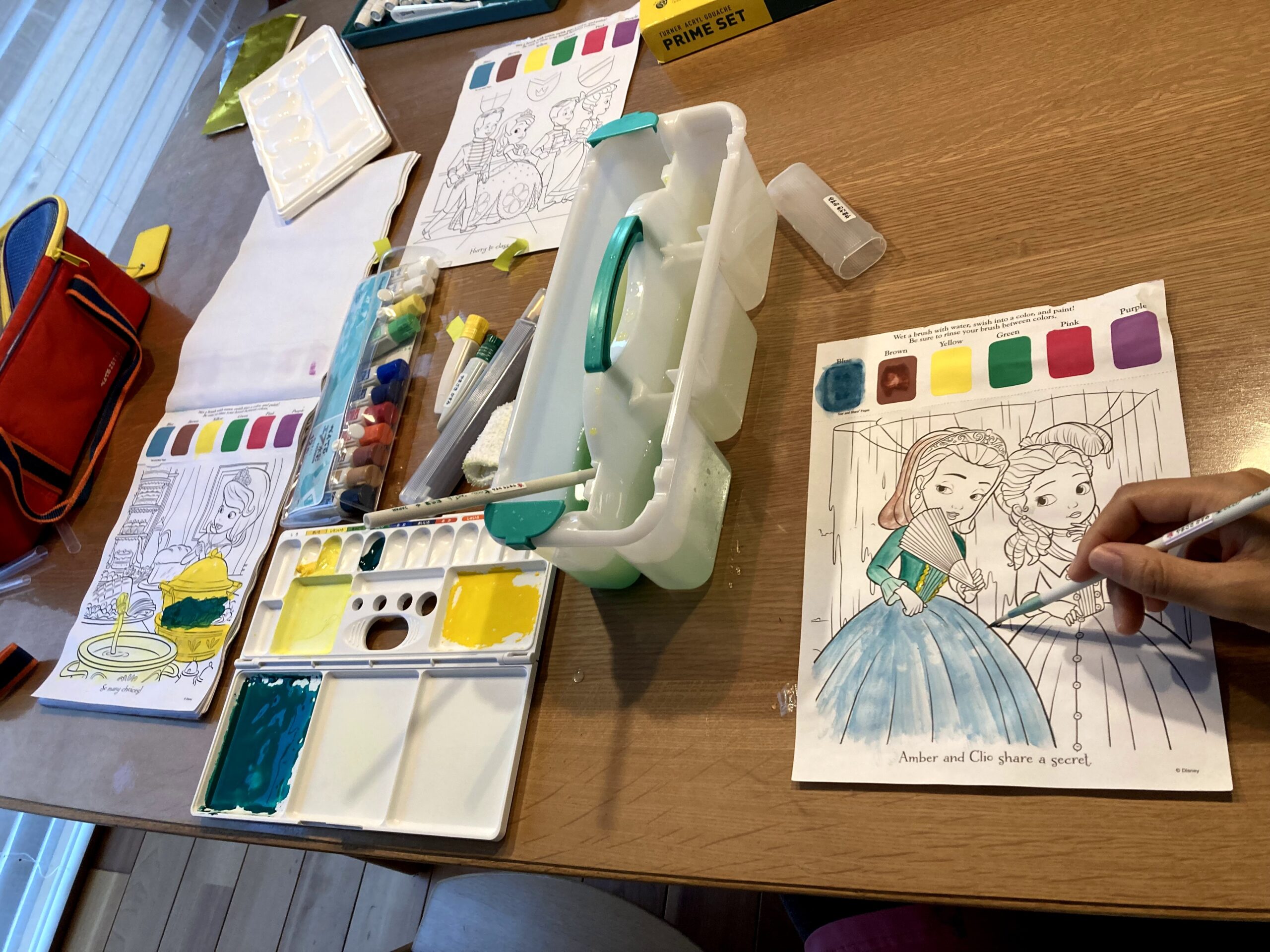

























さきさん
しょぼん、しますよね。
それも小さくないですよね。
大きくしょぼん。うんうん。
うちの長男も診断フルコースで同じ!
今度よかったら話しましょうね。
グレーゾーンの子の方が明確な支援がない時、つらいことだってありますよね。
診断云々じゃなく、この子が困っていることにサポートがあるか?
そこを見ていきたいですよね。
そして療育とか行くと、これって
特性あろうがなかろうが、
子供にとってすごくいい支援、
学びだなーって思うことありません?
選択制でもいいし、みんなにあったらいいのにって。
私の兄は重度知的障害の自閉症なんですが、母が地域で活動していくなかで、
この子にとって必要なことは
社会にとって普遍的に必要なこと
って言ってたことをずっと覚えています。
だから息子が通常学級でiPad使う配慮がなかなか通らなかった時、
それを自分に言い聞かせてました。
あぁ話したいことたくさん!
長くなっちゃったけど、まとめると
埼玉だけど、仲間がここにいますからね^_^
しょぼんが小さくなること、一緒に
考えていきたいですね!
フルコースお仲間ですねー!ぜひぜひ、お話しさせてください!
そして、恵さんの仰ること一言一句同意です。特性あるなしに限らず、この支援は普遍的に必要なのでは?と療育に行くたびに思ってました。
あとお母さまのお言葉も素晴らしい…!うちの長男も、デジタル教科書使用も未だに認められませんが、「この子に必要なことは社会に必要なこと」私も言い聞かせてもうちょっと頑張ろうと思います。
すごく、心強いお言葉ありがとうございます!
あ!iPadのくだりは、
通常学級であっても、その子その子にあった学び方の工夫が普遍的に必要って意味ね。iPadがみんなに必要ってことじゃなく。言葉たらずでしたー
福島さん、しょぼん。って表現
すごく分かりやすいですね。
状況は分かっているけどさ…ってお気持ちがすごく伝わります。
支援が後回しにならないことが理想ですが、せめて後回しだと福島さんが感じずに済んだお答えが発達相談の時にあれば良かったのに。と感じてしまいました。
次男くんの良さも分かっている福島さんが、未来を考えた時に、”困るんだろうな”と不安になるだけじゃなく、どんな面があろうと良い面を引き出してもらえるだろうから大丈夫!って思える環境に出会えますように。
山本さん、ありがとうございます!
そうなんです、後回しなのはしょうがないんですが…でも、山本さんのコメントを拝見して、悲観的になっていても仕方ないので、せめて本人の良い面を引き出して貰える環境づくりを頑張っていけたらな、と思いました、ありがとうございます!☺︎
福島さーん!!!
まさにそのしょぼんが、めちゃくちゃわかります!!!
うちの長男も、うすいグレーだと言われたんです。
本人も、私も困り感があって、環境が変わる新年度は辛かったです。
繊細な子は、先を見通す声かけや、フォローが少しあるだけで過ごしやすくなりますよね。
わがままだと誤解されがちだから、この子が過ごしやすくなるといいよね。と、心理士の先生にも言われました。
入学してすぐ、担任、スクールカウンセラー、相談員の方と4者面談もしました。
ここにいる先輩母たち、小学校の支援をしている方、先生をしているパパ、とにかく沢山話を聞いてもらい、なんとかやってきました。
診断をつけたいわけじゃない!
私たちは、ただただ子どもたちが過ごしやすいようにしたいだけなんですよねぇ。。
正解はそれぞれだから、悩むけれど…
しょんぼりした時は、どんどん話してくださいね!もしここに書いてくれたら、うんうん。ってコメント書きにきますね!
岸さん!わかりますって言って貰えて本当に嬉しかったですー!!
そうなんです!診断ついてもつかなくてもいいんだけど、子どもたちが過ごしやすい環境を作ってあげたいだけなんです…(それが難しいのですが…)
いろいろと難しいですしまたしょんぼりするかもしれませんが、岸さんみたいに周りの人に相談して、過ごしやすくできたらいいなあと思います。
さきちゃん
私も今は息子をこの先どうしたらいいのか分からなくなっていたところ。白黒つけるってだからどうなの、どこまで診断が降りるの、降りたからってなんなんだろう、、他人への理解のために診断しようかと思ったけど、そこから先あるのはなんだろう、と…色々わかんないししょぼんだよなー。さきちゃん、思いのままにそのままに書いてくれてありがとう
かおりん、そうなんだよね… 診断うんぬんだけの問題じゃない。その子が過ごしやすい環境、わがままじゃなくて必要な支援ってなんなんだろう。どこまでお願いしていいんだろう… 悩み悩み中。かおりんに会えてないなあ。ゆっくり話したいなあ。
さきさん
グレーゾーンって何だろうって思いますよね。おそらくうちの娘もそれなのかなと思います。そして私も。障害。と診断されたならば、こどもも大人も〝合理的配慮〟がなされる世の中。でもそれは、世の中的に理解が浸透されてるわけじゃない。じゃあそれ以外の子は?生きにくい中もがくしかないのか…と思い悩む、今日この頃でした。今日はお会いできてほんとに嬉しかったです^_^
ほんと、グレーゾーンってなんでしょうね。私もそれなりに凸凹あるし、人間みんな凸凹で当然だと思うんですよね… その子に必要な支援、理解ってなんだろうなあと日々考えます。
先日はお会いできてお話できて本当に嬉しかったです!また、ゆっくりお喋りできるのを楽しみにしています。