18歳で瀬戸内海に浮かぶ島から上京。
バンドデビューを夢見て独り暮らし。刺激だらけの都会に心を奪われた。それと同時に、不安に打ち克つために無理して虚勢を張っていた。
バイトから戻る狭いアパートの部屋。眠れない暗闇に溜息ばかり数えた。
目を閉じると、旅立ちを見送ってくれた、駅の改札で手を振る母の顔がスローモーションで浮かんで消えた。
「母ちゃん行ってくるよ」あの日、照れ臭くて呑み込んでしまった言葉。
母ちゃんも涙を浮かべた笑顔で、列車が滑り出すまで手を振っていた。もう45年前…春の朝だった。
バンドの夢は叶わなかったが、23歳で作詞家として生き始めた東京暮らし。忙しさを言い訳に数年に一度しか帰郷しなかった20代から30代。
たまに帰る実家のぼくの部屋は、18歳の旅立ちのときのままだった。
唯一増えていたのは、ぼくが関わったレコードたち。母ちゃんが買い揃えていたらしい。どれも聴いた形跡はなく、ただジャケットを眺めていたのだろう。
家族を連れて帰省するようになった頃から、「母ちゃん」から「お袋」に呼び方が変わっていった。
今も東京の夜空を見上げると、旅立ちの朝、手を振る母ちゃんが浮かぶ。そして、吞み込んだ言葉を呟いてる。
「母ちゃん行ってくるよ」
「天国で父ちゃんと仲良くやってる?」
作詞家 池永康記






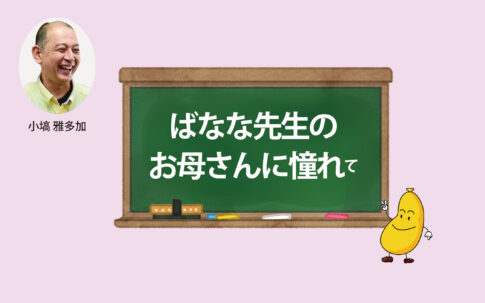

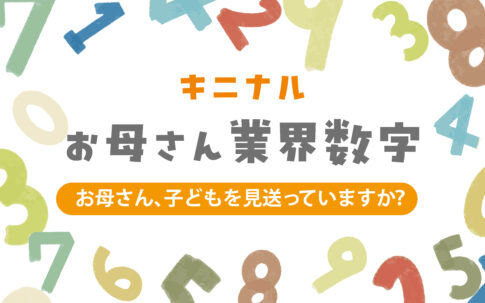























コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。